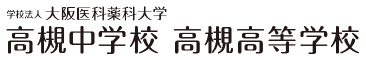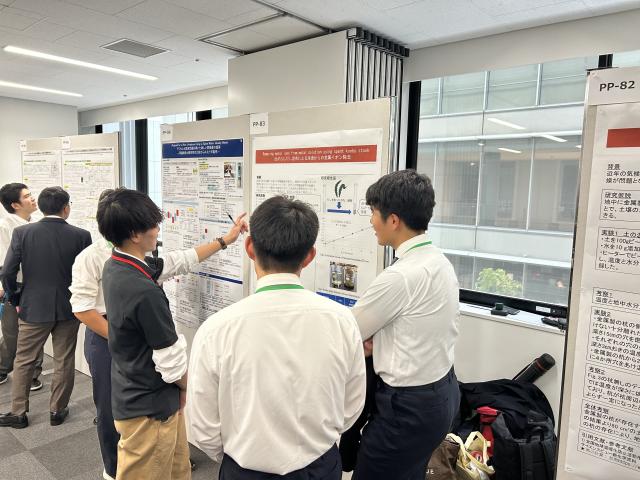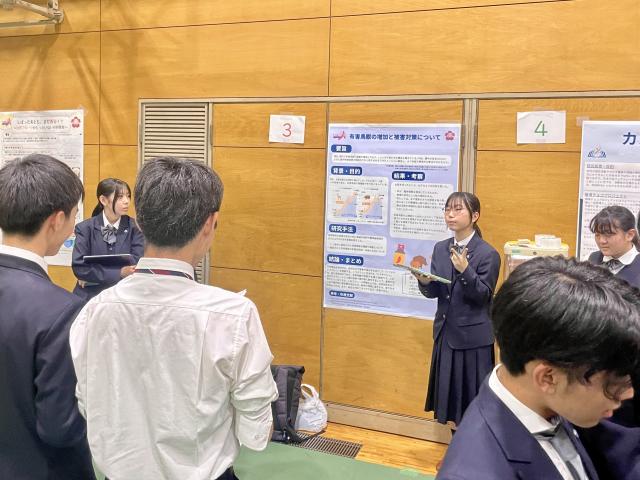10月28日(火)3・4限目、図書館ALCにおいて「JICAの先生に聞いてみよう」を開催しました。高2GAコースの海外研修パラオフィールドワークを目前に控え、講師としてJICAの青年海外協力隊や専門家として活動された3名の先生方をお招きし、お話を伺いました。
講師の先生(活動国/分野)
- 益井 博史先生(ソロモン諸島/青少年教育・読書普及)
- 圓 知愛子先生(パラオ/栄養士)
- 木村 匡先生(トンガ/養殖、パラオ/沿岸生態系管理)
3限目は分科会形式で、それぞれの講師にご講義いただきました。専門分野の視点から、活動成果や体験談、異文化理解のヒント、研究調査のノウハウなどをわかりやすくご紹介いただきました。講義後には、生徒たちの多くの質問にも丁寧にご対応いただきました。
4限目には、3名の講師と44名の生徒が一堂に会し、全体での質疑応答を行いました。進行はパラオ委員が務め、赴任地でのご苦労や、異文化間でのコミュニケーションの工夫などについて、それぞれの講師から貴重なお話をいただきました。実体験に基づいたアドバイスは、生徒たちにとって深くうなずける内容ばかりで、大変有意義な時間となりました。






参加生徒の感想
- 停電、野菜不足などいろいろなイレギュラーが起こりがちなパラオだからこそ人と人との距離が近くて自然と助け合いが生まれているのではないかと、お話を聞いて思いました。また、現地に行った際には心をオープンにしてスポンジ状態で挑むのはよいけれど、研究に関しては整理していったほうが吸収率があがるということを聞けたので、オープンマインドながらも研究はしっかり詰めていこうと思います。
- 実際にパラオで現地の人たちと一緒に働いた先生のお話や、南洋諸島で生活した先生のお話を聞けてパラオに行くのがより楽しみになりました。現地の人たちとうまくコミュニケーションをとれるようになるコツとして、「あいさつ」が大切だと知ったので、パラオでしっかり挨拶できるようにパラオ語を調べたり英語を練習したりしたいです。パラオの文化について詳しく教えてもらうようにインタビューしようと思いました。
- 今日のセミナーで特に印象に残っているのは、海外に行って他国の文化にふれあったときにその人の名前を呼んだり、現地の言葉で何の単語、挨拶のことばを聞いてみることで交流が深まることを教えていただいたことです。
- パラオに渡る日が近づいてきましたが、直前にJICAの先生からお話を聞く機会があってよかった。特に南洋諸島での生活経験をされた先生から体験談を詳しく聞くことができた。先生たちの助言を参考に、学ばせてもらうという姿勢を忘れずにパラオ研修にいこうと思う。