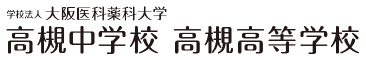6月26日(木)、大阪公立大学 農学研究科 准教授 谷修治先生をお招きし、「微生物の功罪を考える」と題したSSセミナーを開催しました。中学1年生から高校2年生までが参加し、熱心に話を聞いていました。
講義は高校生物で学ぶ内容をベースに構成されていましたが、まだ学習していない中学生にもわかりやすく丁寧に説明してくださり、生徒たちの感想からも、微生物に対する関心の深まりがうかがえました。

参加生徒の感想
- バイオマスなど今の先端技術と身近なカビなどが結びつくのは頭ではわかっていてもやはり驚きました。小さな生物で大きな課題が解決するかもしれないというのは興味深いです。(中1)
- カビと植物を結びつけて考えることがなかったので、とても興味深かったです。技術が発達したらもっとほかのところでもカビを活用できるかもしれないと思いました。(中2)
- 今まで微生物の存在についてほとんど知らず酸素を作ることなど知りませんでしたので、今回の講義で微生物の可能性を知ることができました。まだまだ微生物のことは解明されていないので、これからどのような種類が見つかっていくのか楽しみです。(中2)
- 今日の講演で私は特に谷先生が今実際におこなっているカビの研究が印象に残りました。私には、カビの遺伝子を組み変えることでカビの酵素の生産量をあげるという発想がなかったので驚きました。また、講演の内容とは少しずれてしまいますが、私は今農学部と理学部で悩んでいるので、農学とはどういう学問なのかというお話はとても貴重でありがたかったです。(高1)
- ・微生物が予想以上に多くの分野に活用されていると知って、おもしろかったです。一番驚いたのが、「発酵」と「腐敗」に科学的な違いはないということでした。対義語だと思っていたのに、実際は私たちの文化・習慣・好みによっていいことでもあるし、悪いことにもなり得るということがびっくりしました。納豆の例がとても分かりやすかったです。わたしたちは無意識に人間を中心に世界を考えてしまうけれど、その世界はだいぶ微生物が主要であるんだなと思って興味深かったです。(高1)
- 私は今日の講義の中で、微生物の功罪である発酵と腐敗に一番興味が惹かれました。私たちにとっては腐敗と考えられている「みかんのカビ」などが研究には発酵として考えられていることを通して微生物には本当にいいところしかないのかなと私は思いました。(高2)
- 生物選択なので知っているところもありましたが、授業で習った部分の発展した内容もあり、微生物に対する考えが深まりました。生物は暗記だと思っていましたが、実際に大学の研究を聞いてみて、高校の生物とは全然違っていて社会の役に立つために、多様な微生物を用いる方法や仕組みを考えており、とても難しい学問だと思いました。(高2)