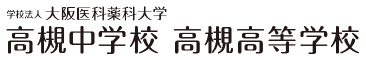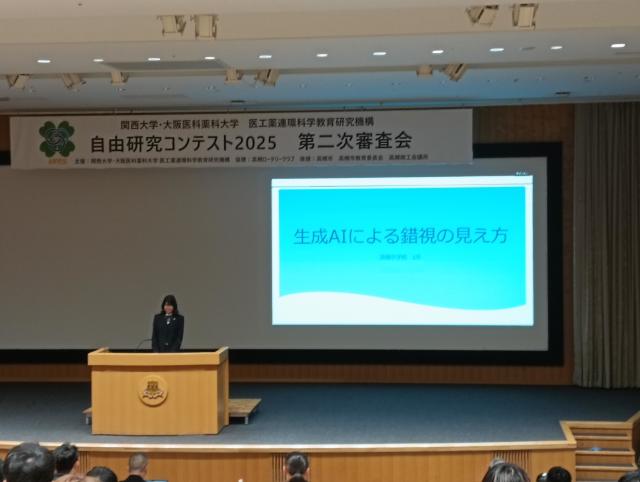11月5日(水)、京都府立大学 土壌学研究室の中尾淳准教授をお招きし、大学0年生講座として「土から離れては生きられないのか?」というテーマでご講演いただきました。本講座は、大学での学びを先取りし、将来の進路を考える上でのヒントを得ることを目的としたもので、今回は「土壌」という一見身近でありながら奥深いテーマに焦点を当てました。
講演では、中尾先生が実際に岩石や土のサンプルを持参され、生徒たちは視覚や触覚も交えながら、土壌の多様性や機能について学びました。土は単なる「湿った砂」ではなく、生物の生存を支える力を持ち、時には災害時の放射性物質の吸着など、私たちの生活を守る役割も果たしていることが紹介されました。また、土を使わない植物工場の話題では、最新の農業技術と土壌の役割を比較しながら、土の持つ「人が認知できない能力」や「人工的に再現することの難しさ」についても触れられました。
講義後には、土壌の色や性質が場所や深さによって異なることに興味を持った生徒も多く、「土の種類についてもっと知ってみたい」との声も聞かれました。身近な存在でありながら、普段はあまり意識することのない「土」に焦点を当てた今回の講座は、生徒たちにとって新たな視点を得る貴重な機会となりました。

受講生徒の感想
- 土を使わない植物工場はメリットが多いという印象が強かったけれど、コストがかかることもあり難易度が高いことを知りました。また土には、人が認知できない能力もあり、人工的につくることは難しいのだとわかりました。雲母に汚染物質をとりこむことができることには驚きました。(中1)
- 土壌を作るのは無理だと知り、土ってすごいんだなと思いました。土は場所や深さによって色などが違うと知り、面白いなと思いました。実物を使って説明してくださったのでとても分かりやすかったです。植物工場で穀物を育てている映像を見たことがなかったので、とても納得できました。土の種類についていろいろ知ってみたくなりました。(中2)
- 福島の原発事故のときとかに土が使われて役に立ったと知り、土ってすごいなと思いました。土って砂が湿っただけだと思ったけど、それだけではなくて、しかも生物が生きたり住んだりするための力を持っていると知れて、今日お話が聞けて良かったです。(高1)
- 黒雲母と白雲母の化学結合を交えた説明がすごくおもしろかったです。これまで、微生物にしか注目していなかったのですが、習った原始の性質などで説明された安定性の違いなどがとても興味深かったです。自分でも原子モデルをつくってみたいなと思います。(高2)